相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続き方法
相続放棄の メリット・デメリット
一般的に親が亡くなった場合は、相続人は親の財産と負債のともに相続します。
なお、相続する財産より負債の方が多い場合に相続たくないと相続放棄の手続きをとることもできます。
この場合、➀相続放棄をした方がよいのか、➁相続放棄はいつまでにしなければならないのか、③相続放棄後は何もしなくてよいについて注意点しなければならないポイントの解説は以下の通りです。
➀相続放棄と手続き方法
相続放棄とは、相続する財産、負債、その他の権利関係を一切引き継がないようにする手続きのことです。相続放棄をするには、相続手続に必要な書類をそろえ、家庭裁判所に申述の申立てをしなければなりません。
➀-1そもそも相続放棄はどんな場合に検討すべきなのか?
相続放棄を検討すべき場合とは、以下のようなケースです。
●負債の方が財産より多いケース
被相続人の財産よりも負債の額を比べたときに負債の額のほうがかなり多い場合には、相続財産で負債を支払いきれないことになります。
こうしたケースでは相続放棄を検討する必要があります。
●他の相続人に財産と負債を相続させたいケース
複数の兄弟で長男に相続させたい場合などや、複数の相続人のうちで、財産の一部を相続させたい場合にも、相続放棄の手続きが必要となる場合があります。
この場合、遺産分割手続きによって、一部の相続人に財産を相続させることができます。
しかしながら、被相続人の負債を遺産分割手続きだけでは、債権者に対して相続人の一部が負債を引き継いだことを主張することができず、他の相続人も支払いの請求を受ける債務者としての義務は残ってしまいます。
このような場合は、遺産分割ではなく、相続人以外の親族は相続放棄を行うことにより、負債を一部相続人に相続させることができます。
●遺産の価値が低く手続きが面倒なケース
不動産は、相続においては登記手続きをしなければなりませんが、不動産が遠方にあるなどなどの場合は管理も大変ですし、固定資産税などの負担も発生します。また、預金などを相続する場合も、払い戻しの請求などの手続きが必要です。
これらの手続きの手間や費用と財産の価値を比較して遺産が少ない場合も相続放棄をする方がいいと考えられます。
➀-2相続放棄手続き4つのステップ
相続放棄手続きのステップ
ステップ1 放棄の資料をそろえる
相続放棄に必要な資料をそろえますが、申述人の立場により必要な書類がかわります。主なものは下記の通りとなります。
共通資料
相続放棄の申述書
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人の戸籍謄本
申述人が配偶者の場合
夫の死亡時の戸籍謄本
申述人が子の場合
親の死亡時の戸籍謄本
申述人が父母・祖父母場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
申述人が兄弟姉妹の場合
被相続人の出生時から死亡までの戸籍謄本
被相続人の父母・祖父母の死亡の戸籍の謄本
*追加の戸籍謄本が必要になる場合がある。
ステップ2 申述書を記入し資料を提出
申述書に記載する本人や被相続人の本籍・住所を記入する。
なお、「相続財産の概略」欄は、提出時点に判明している財産で大丈夫です。また、使用する印鑑は認印ですが、次の照会書と同じ印鑑を使用する必要があります。
記入した申述書と必要書類は、被相続人の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に提出します。
「最後の住所地」は被相続人の住民票除票や、戸籍附票の住所です。管轄の裁判所を調べ、提出します。
申し立ての際にには、手数料として800円の収入印紙と連絡用の切手が必要になります。この必要な切手の額面や枚数は家庭裁判所によって異なりますので、各家庭裁判所に確認してください。
提出を郵送で行うことも可能ですが、この場合は収入印紙なども全て同封します。
ステップ3 家裁からの照会書へ記入し郵送する
申述書の提出から1週間から2週間後に、家庭裁判所から照会書が届きます。(電話による聴取や、何もない場合もあり)
照会書は、申述人と被相続人の関係や、被相続人の死亡を知った日時・経緯、判明している遺産の内容、遺産を費消した場合や、相続放棄の意思確認などの記載する欄があり、これらを記入して返送することになります。
ステップ4 相続放棄申述受理通知書の送付あり
回答書をから1週間から2週間程度で、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。
これは、相続放棄の申述が正式に受理されたという通知の書類で、この書面によって、相続放棄の申述の受理が完成されたことになります。
また、相続放棄申述受理通知書の再発行はありませんので、大切に保管してください。
●相続放棄が完了したあとの手続き
相続放棄が受理されたことを債権者に連絡することになります。
相続放棄後に債権者から負債の請求があった場合は、相続放棄申述受理通知書を提示すれば問題ありません。
しかし、相続放棄をしなかった相続人が預金の相続手続きをする場合には、相続放棄受理証明書の提出を求められる場合があります。
証明書の申請は、相続放棄の申述した家庭裁判所に行いますが、手数料は1通150円(収入印紙)です。

➁ 相続放棄の注意点
相続放棄の手続きは複雑な手続きではないのですが、注意しなければならない点がいくつかあります。
●相続人が複数いるケース
父親が被相続人で、本人を含め子供が3人いる兄弟が相続人となる場合、相続放棄は兄弟全員で行う必要があります。
もしも、本人だけで相続放棄をした場合には、相続放棄をしていない兄弟が、負債も含めて相続することになります。
相続放棄をする際に負債が多い場合には、相続人全員が一緒に相続放棄をするように注意が必要になります。
●相続放棄すると別の親族が相続人となるケース
兄弟全員が相続放棄をした場合に、その結果で新たな親族が相続人となることがあります。
次のような例ですと、亡くなった父親の祖父が存命のようなケースが上げられます。この場合では、兄弟全員が相続放棄を行ったあとに亡くなった父親の祖父が新たな相続人となることになります。
その上に、亡くなった父親の祖父がさらに相続放棄をすると、又は祖父がすでに死亡している場合は、亡くなった父の兄弟姉妹であるおじなどが相続人となります。
このように、相続人の子どもが相続放棄をすることで、それまで相続人ではなかった人が新たに相続人となることがあるのです。
特に負債の相続される場合には、後でトラブルになりますので、相続放棄をした人は放棄が受理されたら、すぐに他の相続人となる人へ連絡して、相続放棄をすることを検討してもらうようにすることが必要でしょう。
●相続放棄の期限
相続放棄は「相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内にしなければなりません。
この「相続の開始があったことを知った時」は、相続人の立場によって違ってきます。
被相続人の妻や子などは、被相続人が死亡した時点で相続人となりますから被相続人が死亡した時が知った時となります。
しかし、本来の相続人が相続放棄をした結果、新たに相続人となった人は、本来の相続人が相続放棄をしたことを「知った時」とは異なります。
もし相続人が相続放棄をしたことを知らなかった場合は、相続人として返済の督促状を受け取るなど、相続放棄の事実を知った日から3カ月以内に手続きをすれば良いことになります。
ところで、例えば負債がどのくらいなのか不明であるなどでは、3カ月以内に相続放棄をするかどうか決められないこともあるでしょうから、その場合にはどうすればよいのでしょうか。
その場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸ばす申立てをすることで、3か月の期間を延ばしてもらうことができます。手数料は800円です。
なお、伸長の申立ては熟慮期間内にする必要があることを忘れないように注意してください。
➁-4相続放棄ができないことはあるのか
3カ月の熟慮期間中に、相続放棄の申述や熟慮期間の伸長の申し立てをしなかった場合には、相続放棄をすることはできません。
さらに、熟慮期間中でも被相続人の預金を払い戻してしまった場合など、相続すべき財産を費消してしまった場合や財産を処分した場合も、原則として相続放棄はできなくなります。
相続放棄の可能性がある場合は、被相続人の財産に手をつけないよう、十分注意しましょう。
➁-5相続放棄によって失われる財産
相続放棄は、相続人が被相続人の有していた一切の財産を相続することができなくなることです。
例
● 預貯金、 株式・国債等、 不動産、 自動車、 時計、 宝石・貴金属など
なお、被相続人が生命保険の受取人として相続人を指定していた場合は、お金を受け取る権利は指定された相手の権利となるために相続放棄にかかわらず保険金は受け取ることができます。
➁-6 相続放棄しても管理義務責任は残る
相続放棄をすると、被相続人の財産を管理する義務は逃れることになります。しかし、相続放棄をしても、他の相続人が管理を始められるようになるまでは引き続き財産の管理をする義務は残ります。
たとえば、危険な土地や建物など土砂崩れなどによって他人に損害を与えた場合には、相続放棄をしていても責任を問われる可能性があります。
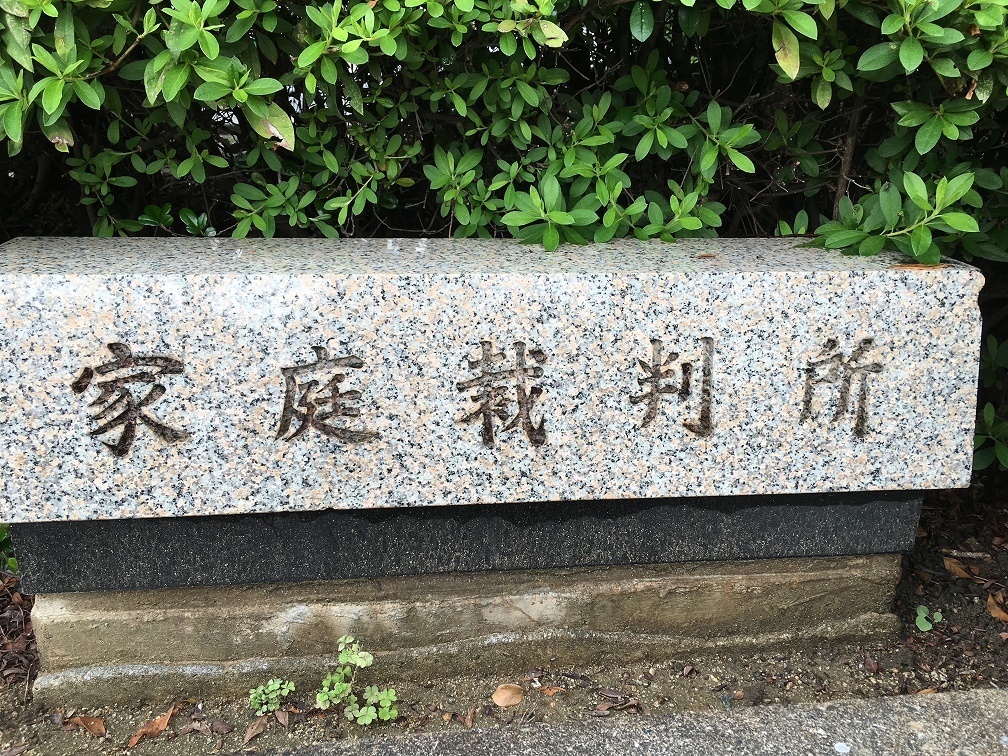
③ 熟慮期間内に相続放棄ができなかった時は?
3カ月の熟慮期間内に相続放棄をしなかった場合は、原則として相続放棄はできません。
例外的に放棄が認められるケース
③-1
3カ月を経過していても相続放棄が認められる場合
● 相続人が相続財産を存在しないと信じていた
● 被相続人の財産の有無の調査をすることが困難であった
● 相続財産がないと信じた相当な理由があった
具体例
「疎遠で財産はないと考えていた」
「海外在住で財産調査に限界があり、想定外の債務が突然出てきた」
「生活状況から借金があると考えられなかった」
なお、財産があることを知っていたが、後に財産をはるかに上回る債務が発見されたというようなケース。
③-2 熟慮期間を過ぎた場合の対処法
・相続放棄の手続きを行う
熟慮期間の経過後の相続放棄では、熟慮期間を過ぎた理由を説明する必要があります。
相続放棄申述書を提出した後の家庭裁判所から送られてくる照会書で、熟慮期間を経過してしまった理由について照会書に記入して説明しなければなりません。
その理由が「熟慮期間経過後に相続放棄が認められる条件」に該当するかどうか、という点です。
家庭裁判所にわかるような記載が必要です。慎重に十分に注意しましょう。
まとめ
相続放棄は決して難しい手続きではありません。一般的なケースであれば本人が行うことも十分に可能です。
ご相談お申込みフォーム
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com



