相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
自筆証書遺言の保管制度とは?
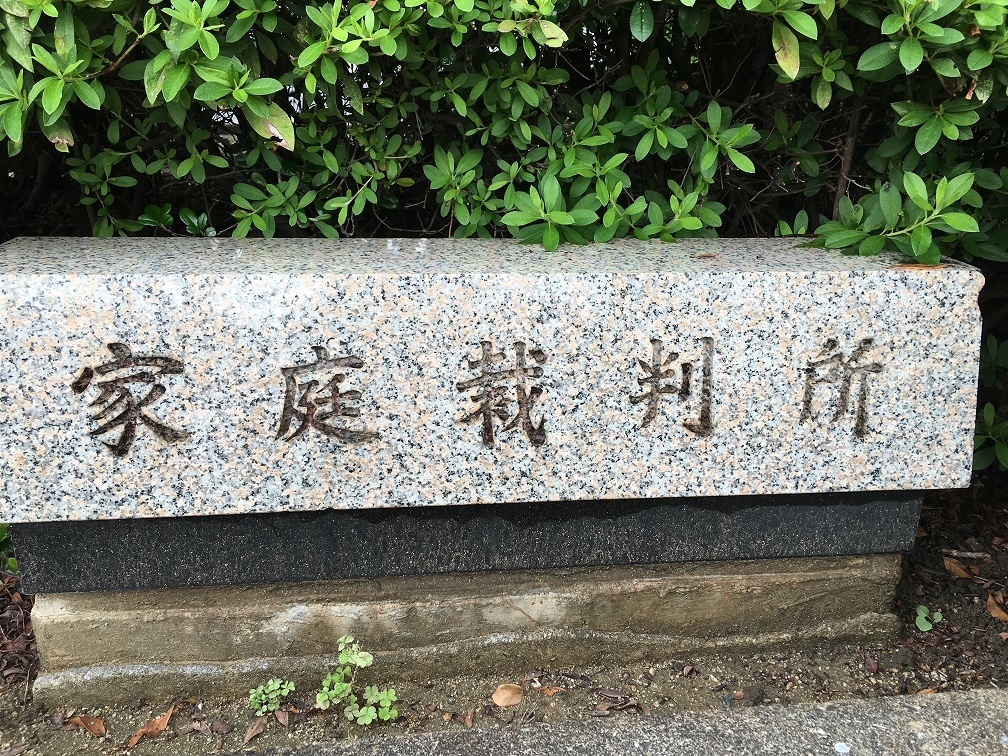
自筆証書遺言の保管制度とは?
自筆証書遺言の保管制度のメリットやデメリットについて
自筆証書遺言作成の法務局予約の方法は3つ
①ネット予約
法務局手続案内予約サービスから予約。
②電話予約
手続きを行う法務局へ電話で予約。
③窓口予約
法務局の窓口で予約。
ネット予約は24時間予約が可能
なお、法務局は、ご本人の住所地・本籍地・所有不動産の所在地の3つから選択することになります。多くの方が住所地の法務局を選択すると思われます。
当日は遺言書・保管申請書・必要書類を揃えて窓口へ
「遺言書保管窓口」に行き、自分の名前と予約時間を伝え手続きの開始です。
持参する書類は、以下のものです。
・自筆証書遺言(自分で書いた文案)
・遺言者の住民票(本籍地入り)
・遺言書保管申請書(3,900円の収入印紙を貼付したもの)
・本人がわかる身分証(免許証や保険証、マイナンバーカード)
難しい書類は必要ありません。
遺産を遺す相手の戸籍謄本も、本人の戸籍謄本も不要です。
手数料の収入印紙代(3,900円)は、法務局の収入印紙売り場で購入できます。
・窓口では家族や知人も同席が認められず本人自身で法務局の職員との対応になります。
遺言により財産を受け取る家族や相続人と法務局に行っても、窓口の職員から
「席に座りお話をするのは遺言者だけです。ご同行の方は後ろでお待ちください。」と言われます。
予約した本人しか窓口では対応してくれず、例え家族や配偶者も同席は認められません。
*本人の体調不良とか、会話できないようなそれなりの事情があれば同席を認める場合もあるようです。原則として本人のみとの対応のようです。
行政書士などの士業の同席も認められない方針です。
本人が高齢者の場合は、不安が残ります。
無事に遺言書を受け付けると「保管証」が発行されその場でもらえることになっています。
*保管証とは
法務局の担当者が内容を確認し、形式上の問題がないことを確認すると窓口でもらえるのが「保管証」です。
なお、保管証を受け取る際に、遺言書保管についての説明があります。
法務局に預けた遺言書には保管番号が付けられ管理されるようで、変更等の届出や遺言書情報証明書を相続人が請求する場合には、保管証が必要になるようです。
(ただし注意が必要ですが再発行はできないとのことです)
これまでの手続には、30分ほどかかります。
この保管証を受け取り手続きは終了です。
この手続きを利用して気付いたこと
自分で遺言書を書くことは、大変だということです。
それは、自分の遺言書を作ってみると、細かな点で分からないことがあったり、意外と大変で勉強になりました。
これからご自分で書かれる方ために注意点として、いくつか指摘させていただきます。
➀A4の便箋探しで苦労しました
この自筆証書遺書保管制度では、提出する書面のサイズは「A4サイズ」と決められています。ところが、A4サイズの便箋売っていないのです。便箋のサイズはB5です。A4サイズの便箋などは売っていません。
➁自筆証書ですから全文自署です
自筆証書遺ですから自署すると分かっていたのですが、書いてみると大変さに驚くでしょう。
それは、納得のいく遺言の文章を書くことができないことです。何枚書いても綺麗に書けないことでしょう。問題はそんなに難しい財産内容の遺言ではないのですが、書きなれていないのであきらめるしかないと思いましょう。
問題は、ご高齢な方が書く場合です。ご本人は、大変だと思います。
財産を別紙で特定する方法も悩ましいです
不動産は、登記簿謄本を取得します。しかし、マンションの場合は、登記簿が2ページになり一般の方は難しいでしょう。法務局へ確認をしましたが、「1つのマンションなら1ページ目に別紙1と書けば2ページ目には何も書かなくていい。」という答えでした。
この部分ですが、あとで疑問がわくことになります。
遺言書の余白が問題となります
保管する遺言書や別紙には余白(上と右は5mm、左は20mm、下は10mm)をあけなければいけないことになっています。
法務局の職員が定規で測ります。補正させられることも多いでしょうが、注意すること必要です。
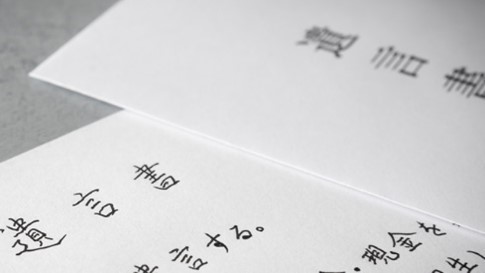
まとめ
➀法務局は遺言書の保管だけ
私たち専門家は、法律上不備・漏れの一切ない内容の自筆証書遺言を作り上げることができます。
しかし、制度を利用するのは一般の方々ですから、問題のある内容の遺言書を保管してしまう問題が必ずあります。
法務局は審査するといいますが、それは遺言の形式面だけです。(自筆証書遺言の要件や保管制度の手続き要件)
内容については一切しませんし、できません。
➁法務局は全く相談を受けません
窓口で受け付けている法務局の方は、遺言について一切の相談・アドバイスを聞いてくれません。法務局のパンフレットには小さな文字で書いていますが、質問を受けてないようになっています。
それは、遺言書の内容で争いが起きたときに法務局が巻き込まれることがないようにするためでしょうか。法務局は、単に遺言書を預かるだけの立場です。遺言の内容が原因で争いになることになったとしても、あくまでも保管した本人の責任ということです。
さらに自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらに使用か聞いてみると、専門家に聞いて下さいと言っていました。
③法務局に保管した自筆証書遺言は意思能力の担保にはなるか?
自筆証書遺言で争いになる点の多くは、本人が自分の意思で書いたのかどうかという点です。公正証書遺言は、公証人が本人確認及び意思確認を行いますから、意思能力は担保されるのが当然ですが、法務局であずかる自筆証書遺言には、それがありません。
保管制度を利用すれことは、法務局の職員が対面で手続きを行いますから意思能力の担保にはなりそうだと思いますが、あくまでも遺言を保管するだけという立場です。ですから、受け付けただけで、本人の意思能力は一切保証しないということになるのでしょう。
さらに筆跡鑑定などあるわけではないので、持参した遺言書は本当に本人が書いたかどうか法務局の職員は一切確認をしないことになります。
➃内容不備の自筆証書遺言の量産をしてしまう?
法務局はあくまでも受け付けた自筆証書遺言を保管するだけです。内容についてはアドバイスをしてくれません。
結局のところ、形式だけで法務局は保管を受け付けますので、遺言内容に不備に気が付くのは、本人が死亡した後です。
手続きは簡単で費用も安い遺言を書けることになりました。しかし、実際に遺言を執行する時点で遺言の不備に相続人が気づき、相続人に迷惑がかかってしまう事態が多くなると予想されます。
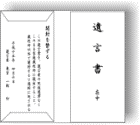
⑤自筆証書遺言保管制度のメリット
●検認がいらない
家庭裁判所での検認がいらないことはメリットです。検認手続きは非常に時間がかかり面倒です。何といっても他の相続人と顔を合わせることは、精神的にも厳しいことがありますので、検認の回避ができることは非常に相続人にとってはありがたいことです。
●死亡時に指定した人に遺言書の保管を通知してくれる
これは公正役場で通知してくれればいいなと思います。公正証書遺言の場合でも遺言者が死亡した時に遺言が見つからなければ意味がありません。しかし、保管制度を使えば死亡時に通知人へ法務局から通知がいくので、確実に遺言が実現すうことになります。
●遺言書を保管しなくて良い
自筆証書遺言の欠点には、保管する場所に困るという点でした。発見できない場所にしまったら、遺言の存在を知られないまま遺産分割をされてしまう可能性がありましたし、見つかりやすい場所だと相続人に知られてしまい隠されたり破棄されるリスクがあります。遺言書が法務局に保管されることで、誰にも内容を知られることもなく、死亡時通知人へ通知されることで発見されないというリスクもありません。
⑥遺言書を保管した後に気づいたこと
法務局を利用する点で、本人にとって面倒なことがあります。
3
➀遺言者の変更届がとても面倒です
本人の氏名、出生年月日、住所、本籍、戸籍の筆頭者、電話番号のいずれかに変更があった場合は、変更届をしなければいけないということです。なぜ、生年月日があるのか、理由は不明です。
変更の可能性が高いのは、住所、本籍、電話番号だと思いますが、これらに変更があった場合に法務局へ届出をしなければいけないのは非常に大変です。
多分、実際に変更が生じても法務局へ変更の届出できないケースが多く発生すると思われます。それは、本人が高齢の場合に多くあると思います。
➁受遺者・遺言執行者・死亡時通知人の住所変更届は忘れる?
本人だけではく、遺言執行者などの住所変更が生じたても同様に変更届をしなければいけません。しかし、遺言執行者などは本人に言わずに住所変更等をしても、それに本人は気がつかないままになってしまうことも大いに考えられます。また、本人が死亡した時に通知する住所が変わってしまえば、当然のことながら、死亡したとしても法務局から通知が届くことはありません。
さらに、遺言者が高齢になり認知症等になってしまった場合には誰が変更届をするのでしょうか。
③検認は不要でもすべての戸籍謄本を集めなければいけない
検認が不要という保管制度のメリットが強調されています。でも、遺言者が死亡した後で、遺言書情報証明書の取得をする段階で、出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の住民票を要求されます。これは、検認で出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の住民票を求められるのと同じ手間です。
➃遺言書情報証明書とは
法務局の保管制度を使えば家裁での検認手続きを省略することができますが、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本や相続人全員の住民票を取得する手間は変わらないで、手続きが簡単になるわけではありません。
なお、公正証書遺言では、遺言者の死亡記載の戸籍と、財産を受け取る相続人の戸籍謄本だけでに執行できますから、実は非常に手続きは楽です。
⑤保管制度の公正証書遺言にたいする影響
自筆証書遺言保管制度が開始されると、公正証書遺言の件数に変化があるのか気になっていました。
しかし、自筆証書遺言で済ますのと公正証書遺言を作ろうと考える方は、相続について別なお考えではないかと思います。
⑥自筆証書遺言保管制度のまとめ
自筆証書遺言の保管制度は、使い勝手がいい反面、手続きとして未完成ではないかと感じます。
それは、自筆証書遺言は、ご本人がまだ若く自分で考え動ける方に向いていて、公正証書遺言は高齢な方向きの手続きではないかと思われます。
しかしながら、専門家の立場からおもうことは自筆証書遺言保管制度を使うのなら、費用はかかりますが、必ず専門家のアドバイスを受けることをお進めしますし、その上で利用していただきたいということです。
せっかく作った遺言でご家族が揉めてしまってはなんの意味がありません。自己満足で家族の不満が争いになる遺言が増えないことを望みます。
ご相談お申込みフォーム
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com



