相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
任意後見制度と任意後見監督人の関係
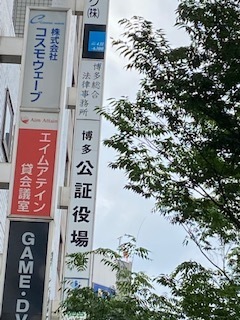
任意後見制度と任意後見監督人の関係
1. 任意後見制度とは
そもそも、任意後見制度とは、認知症などで将来、判断能力の低下に備えて、自分の財産管理や身の回りの世話を任せたい人を任意後見人として契約で定めておく制度です。
預貯金の管理や介護制度の手続きなどの利用を支援してもらいたい人(任意後見人)と契約書を交わす制度を任意後見契約といいます。元気なときにあらかじめ自分が信頼できる人に頼んでおけますので、柔軟に利用できる制度と言えます。
なお、任意後見契約を結んだからといって、任意後見人はすぐに後見のお世話をスタートできるわけではありません。任意後見契約の締結をしてから、本人の判断能力が低下してきたと判断したときに、本人自身や任意後見契約の受任者が、家庭裁判所に申し立てて、開始することになります。家庭裁判所は、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任することになります。
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約書によって決めた内容がスタートすることになり、任意後見人は業務を開始することになります。家庭裁判所により、任意後見監督人が選任されるまでは、後見業務を行えませんから、任意後見契約書に付随して一般的に「見守り契約」といわれる契約を本人とむすび、将来、任意後見人となる人が本人と定期的に面談するというケースが多く行われています。
2. 任意後見監督人とは
任意後見監督人の仕事は家庭裁判所に代わり任意後見人を監督することです。任意後見制度では、家庭裁判所に本人又は任意後見人が判断能力の低下した本人の財産管理等をするために任意後見監督人の選任を申立てることにより選ばれます。
2-1. 任意後見人を監督するとは
家庭裁判所に代わって任意後見人の業務を監督する役目が任意後見監督人の仕事です。定期的に任意後見人は、任意後見業務内容について任意後見監督人に報告をして不正がないか、財産管理などが適正に行われているかどうかをチェックします。
2-2. 任意後見人とどこが違うのか
本人は、自分の信頼できる人を任意後見人に選ぶことができます。しかし、任意後見監督人を選ぶのは家庭裁判所です。本人もしくは任意後見人は、任意後見監督人の選任を申し立てるときに任意後見監督人の候補者を立てることはできますが、家庭裁判所は候補者を選任してくれるとは限らないのです。
2-3. 家庭裁判所がだれを任意後見監督人に選任するか?
家庭裁判所が、任意後見監督人に弁護士などの法律専門職を選任するケースが多いようです。なお、法律には専門職でなければなれないということはありません。
任意後見監督人に選任されない人
① 任意後見人
監督を受ける人と同一人物となり監督の意味がありません。
② 任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
任意後見人の利害関係者は、客観的な監督ができないと思われます。
③ 本人と訴訟で争ったことがある。また配偶者や直系血族。
④未成年者
⑤破産者
⑥行方不明の人

3. 任意後見監督人の職務
3-1. 任意後見人からの定期報告を受ける
任意後見人は、定期的に任意後見監督人へ財産管理等の報告をしなければなりません。一般的には、3カ月に1回になっているようです。
3-2. 家庭裁判所へ定期の報告
任意後見人が定期的に報告をした内容を年に1回、任意後見監督人は管轄の家庭裁判所に報告をします。家庭裁判所は、任意後見監督人が任意後見人を監督し、さらに任意後見監督人を監督することで、任意後見業務の適正な遂行をチェックしています。
3-3. 任意後見人と本人の利益が相反行為
本人と任意後見人の利益が相反する行為は、任意後見人が本人を代理することはできません。
例えば、任意後見契約で任意後見人の権限として遺産分割協議の代理が含まれている場合は、任意後見人が本人を代理して遺産分割協議に参加できます。
この場合に、本人と任意後見人が親族である場合は、ほかの親族の相続手続きを行う場合に、ともに相続人になることもあり得ます。このケースで遺産分割の話し合いを行うときに、任意後見人が本人の代理人として遺産分割協議に参加すると任意後見人は自分も相続人ですから、本人の代理人という2つの立場をもつことになります。つまり、任意後見人が自分の利益になるよう本人の地位を利用することができることになってしまいます。
利益相反の場合には、本人の不利益を避けるために別途代理人を立てなければなりません。この場合には、任意後見監督人が本人と任意後見人の利益が対立するとして本人の代理人として法律行為を行うことになります。
3-4. 緊急の場合
任意後見人が病気等で任意後見業務をできない場合は、任意後見監督人が代わりに緊急の処理を行うことができます。
任意後見人の業務内容は、主に財産管理や身上監護です。財産管理は、たとえば本人の預貯金の管理で、本人の日常生活に必要な金銭を引き出しや各種支払い行為です。身上監護は、本人が適切な医療や介護サービスなどを受けられるように施設や病院の選択などがありますが、これを本人に代わって契約、利用する業務などです。
3
4. 任意後見監督人の申立てから後見開始まで
4-1.任意後見契約は公正証書で締結します
任意後見契約は判断能力が確かなうちに本人の信頼できる人と締結します。任意後見契約は公正証書で行います。公正証書は、公証人が、作成する公文書で作成後に金融機関等に提出しますので公正証書で作成します。公証人が任意後見契約書を作成し、公証役場で東京法務局に本人と受任者の名前を登記します。
任意後見人の受任者は、特に制限はありません。本人が信頼できる人ならば親族にお願いしてもよいですし、行政書士などの法律専門職で信頼できる人に依頼するのもよいでしょう。
4-2.任意後見監督人の選任申立てに必要な書類を準備する
任意後見監督人の選任申立ては、本人の判断能力が低下したときに、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。通常は、任意後見契約書で契約した受任者が申立を行うことになります。
選任申立て必要書類
① 任意後見監督人選任申立書
② 本人の戸籍謄本
③ 本人の住民票または戸籍附票
④ 本人の診断書
⑤ 本人情報シート
⑥ 本人の健康状態に関する資料
⑦ 任意後見契約書の写し
⑧ 登記されていることの証明書
⑨ 本人の財産に関する資料
⑩ 本人の相続財産に関する資料
その他の申立てに必要な資料
申立て資料は、各地域の裁判所指定の様式を使用します。診断書は各地域の医師会の様式に本人の判断能力を診断しますから本人の主治医に書いてもらいます。
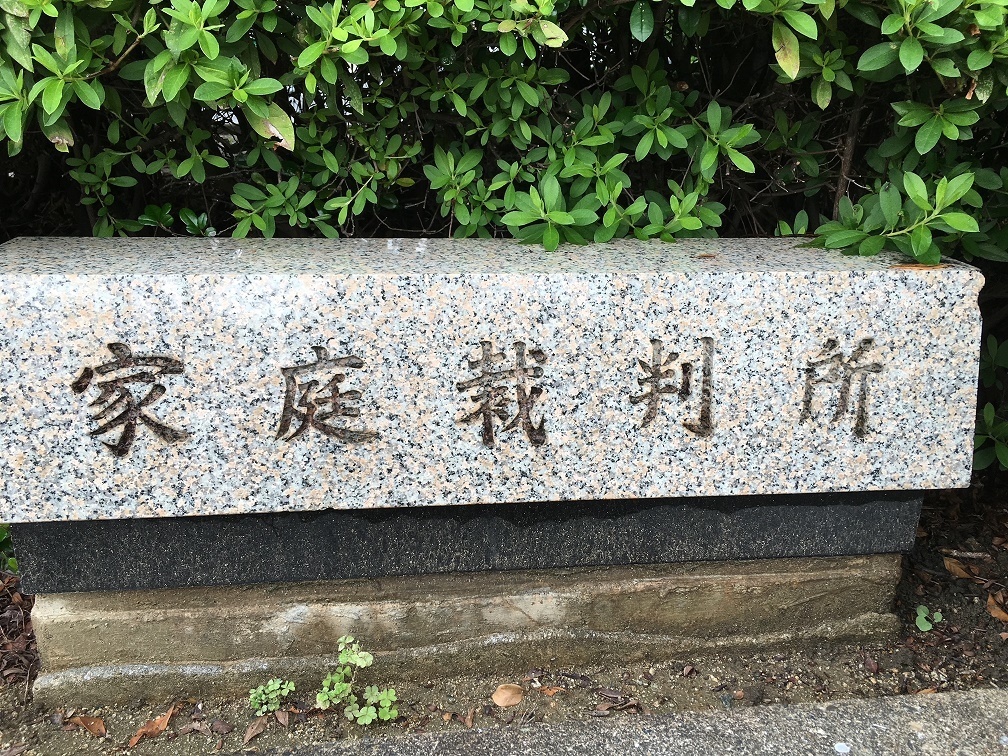
4-3.本人の住所地を管轄する
家庭裁判所に申立をする
申立人
本人、任意後見受任者(配偶者及び4親等内の親族)、
申立の費用(福岡県)
収入印紙 800円分 申立手数料。
収入印紙 1400円分 後見等登記の手数料。
郵便切手 2650円分
4-4.家庭裁判所の裁判官により任意後見監督人が選ばれる
任意後見監督人の候補者がある場合には、家庭裁判所にその旨を記載した書面とと
もに、候補者の住民票又は戸籍附票を提出してください。ただし、裁判官は様々な事
情を考慮して任意後見監督人を選任するため、候補者が選任されるとは限りません。
4-5.任意後見の開始
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。任意後見人は、法務局から任意後見登記事項証明書を入手して、各種手続き先の機関に提出して、任意後見契約で決めた代理業務を行えます。
5.任意後見監督人の報酬
任意後見監督人の報酬は本人の財産から家庭裁判所が決定して支払われます。任意後見監督人が家庭裁判所に報酬付与の申立てを行うことになります。
なお、任意後見人監督人が、特別な業務を行ったときには付加報酬を加算されるケースもあります。付加報酬は、たとえば本人と任意後見人が親子関係で利益相反しているときには、任意後見監督人が本人を代理して遺産分割協議に参加できますが、このようなケースでは報酬が発生することになります。
6. 任意後見監督人の解任はできるか
任意後見監督人と「相性が悪いから」などの理由から解任することはできません。
任意後見監督人に、不正な行為などの理由があれば、家庭裁判所への申立てをして家庭裁判所が職権により解任します。
まとめ
判断能力が低下した本人の財産の管理や身上監護をする任意後見人を選ぶことは、本人にとって大切なことです。将来を安心して任せられる任意後見人は納得いくまで専門家のサポートを得ながら選びましょう。
ご相談お申込みフォーム
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com



