相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
これがホントの公正証書遺言サポート
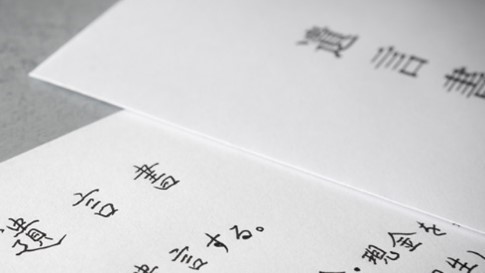
遺言書は公正証書遺言が最も多いのか?
公正証書遺言は、自分が手書きする自筆証書遺言と比較して、公証役場で作成するので、確実な遺言書といわれています。
では、この公正証書遺言の確実性について解説をしたいと思います。
その前に、遺言書の読み方を「遺書」イゴンや、「遺言書」ユイゴンショとどちらが正確な読み方かよく聞かれますが、正しくは「遺言」イゴンです。
公正証書の直近データ
さて、現在多く利用されてる公正証書遺言についてお話しします。公正証書遺言の作成に関するデータでは、「遺言公正証書の作成件数について」日本公証人連合会HPによると以下の表の通りです。
平成28年 10万5350件
平成29年 11万0191件
平成30年 11万0471件
令和元年 11万3137件
令和2年 9万7700件
になっております。
日本公証人連合会によりますと平成元年の作成件数では40935件になっていますから、現在は年間の作成件数が2倍以上に増加しています。
なお、令和2年に下がっているのは、2つ理由からだと思われます。それは、自筆証書遺言の保管制度の開始とコロナにより高齢者が外出を控えたものだと思われます。
また、一般の方が公正証書で遺言を作るメリットとしては、「公証人」が作成に関与するので、遺言書が公文書とし取扱われます。
相続トラブルが予想される場合に、公正証書遺言を作成しておくことで、トラブルなく相続手続きをすることができます。
自筆証書で遺言を作成している場合に、遺言者本人の意思で書かれたものかという疑いを相続人の間で争いになることも予想されますので、公証人が関与する公正証書遺言は争いをさける意味では「強い遺言書」ということになるのです。
公正証書は意思能力が争われることになりにくい
自筆の遺言書が残された相続の紛争の多くは、「作成当時の意思能力」の問題となっています。しかし、遺言書が公証人と証人2名の立会いで作成された公正証書遺言であるならば意思能力で争うことは考えられないことになります。
たとえ現在は仲の良い兄弟であっても、相続が発生した時には争いがないとはいえません。争いを防ぐ目的としての公正証書遺言を作る意味は非常に大きいものといえます。
公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の作成を選ぶ一番の理由は遺言の有効性にあると言えます。公正証書遺言は公証役場で公証人により作成されるので遺言の要件が不備で無効になることは考えられません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は作成者が遺言の不備に気付かず作成することもありますので、作成した遺言が無効になる恐れはあります。また公正証書遺言のように公証人など第三者が作成に関与しないので、自筆証書遺言は、推定相続人などの詐欺や強迫等があり作成者の真意でない遺言が作成される可能性もあります。
さらに、公正証書遺言は家庭裁判所による遺言の検認作業が省略されます。検認は遺言の形式的に有効に作成されていることを調査することです。自筆証書遺言(法務局保管を除く)は検認作業が行われますので、相続手続きにおいて家裁の検認申立てという手間が発生します。
公正証書遺言は確実に有効な遺言を残したいときに効力を発揮します。また原本は公証役場に管理されますので遺失や破棄など、遺言が発見されないというような心配もありません。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、公証人の前で財産を公表することになります。それは、公証人に作成手数料及び報酬を払う必要があるからですが、財産内容の調査、書類収集等などで自筆証書遺言より作成するのに手間がかかり、作成に時間もかかることになります。
なお、確実で有効な遺言を作成したい方は公正証書遺言を選択すべきでしょう。
遺言の作成は公証役場で作る
公正証書遺言とは、公証人が証人二人の前で遺言者が遺言の趣旨を口述を筆記して、遺言者及び証人に読み聞かせたものです(民法969条)。
現在では公正証書遺言で多くの方が遺言書を作成しています。
福岡県内においては、公証役場は、11か所あります。
公証役場にいくことができない人は?
本人がご高齢や体調不良で公証役場に行くことができないには、公証人による出張や自宅や病院・施設に訪問する方法もあります。出張費用がかかりますが、公証役場にいくことが難しい場合には利用することもできます。
公正証書遺言を作成前にする2つのこと
公正証書遺言の作成前に、①財産目録の作成と②財産を遺す相手を決めるということをする必要があります。この2点を決めていないのにいきなり公証役場へ相談をすることはできません。
① 財産目録の作成
最初に財産の洗い出しを行うことになります。預貯金、不動産、株式などです。預貯金については、通帳等を確認して通帳のNoも確認するようにしましょう。
1.預貯金…通帳No確認。
2.不動産…「固定資産税納税通知書」の評価額を確認します。
3.株式…証券会社の「取引残高報告書」で確認します。
② 遺産を遺したい人
ご自身が誰に財産を遺したいのか決めます。きちんと確定しましょう。一応決めるだけで、おおまかな形でよろしいでしょう。
なお、財産を決める方法の一つとしては、金額を指定しないで割合で指定することです。将来お金があるか分かりません。
ダメな決め方
1.子どもらにそれぞれ500万円。
2.長男には1000万円、不動産は長女へ。
公正証書遺言の作成の流れ5つ
公正証書遺言を作成する流れ
①原案作成
③ 書類の準備
④ 公証役場の原案、必要書類の提出
⑤ 公証人との打ち合わせ
⑥ 本人確認
⑦ 公正証書の作成日当日

公正証書遺言作成7つのステップ
① 原案作成
遺言書の原案は公証人が考えてくれません。自分で作らなければいけません。財産を誰に相続させるのか、考えて原案を作ってください。遺言書の原案の作り方がわからない方は、最初から相続相談センターの行政書士に依頼されることをお勧めします。
② 書類の準備
原案作成と並行して準備する必要書類は、本人の印鑑証明書・財産資料・住民票・戸籍謄本です。財産を遺す相手の戸籍謄本と住民票も必要になります。
③ 原案と必要書類の提出
遺言書の原案と必要書類がそろったら、公証役場に持参します。不備なく準備することができたら、実行日の予約が取れます。
④ 公証人との打ち合わせ
公証役場とは、原案の打合せが必要なのでご依頼の場合には1~2週間ほどの時間を頂いています。なぜなら、遺言書の原案では公証人との打合せが大切で、遺言書に記載する財産については正確で、特定が容易な内容でなければいけません。また、不動産については登記簿謄本を、預貯金口座については通帳のコピーを、それぞれの相続財産の価額を証明するもので不動産であれば市町村役場で取得する固定資産税評価証明書を要求されます。そこで、ある程度の時間をかけ公証人と打合せを行うことになります。
⑤ 遺言の作成実行当日
公証人と遺言書案の調整をして実行日を決め証人2人を同行し、公証人と一緒に作成の手続きを進めていきます。公証人手数料は事前に聞いておき、実行日に現金で持参します。
本人が公証役場へ行くことができない場合には、公証人に出張してもらうことができます。ただし、事前に公証人と相談をする人用があります。
作成日当日の流れについて
公正証書遺言作成「当日」は公証役場の部屋ですが、出張の場合は自宅・病室・施設等の会議室などになります。
この当日については、皆さんが不安に感じる部分のようなので、作成当日の流れについて説明をします。
公正証書遺言の作成当日
① 公証人が挨拶します
② 遺言者と証人2名に公証人が本人確認をして、質問を受ける場合があります。
③ 公証人が事前に提出した原案を遺言者及び証人に読み聞かせます。
④ 遺言者と証人は、遺言内容が正確なことを確認して、それぞれが署名押印をします。なお、証人は、認め印ですが、本人は実印であることを確認を受けます。
⑤ 公証人は、方式に従い真正に作成された旨を付記し署名押印をします。
このような流れで進行していきます。
当日にどのような感じで進んでいくのか、もう少し詳しく説明しておきます。
① 公証人の挨拶
遺言者と証人2名が待つ部屋に公証人が入ってきます。そして、公証人が名前を告げて挨拶をします。
「公証人の●●です。宜しくお願いします。」
公証人の中には名刺を出すこともありますが、ほぼ普通は口頭の挨拶だけで始まります。
② 遺言者と証人2名は、公証人から本人確認をされます。
公証人は、この会話の中で本人確認の質問をして答え、態度、言動で、本人の意思能力を確認しています。ご本人は、氏名、生年月日、住所、遺言内容など、受けた質問に明確に答えてください。ところが、高齢な方は緊張してうまく回答ができなくなってしまうことがあります。とにかく、落ち着いて答えることが大切です。
なお、公証役場に同行した親族は同席できませんので、本人は1人で回答しなければいけません。とくに事前に伝えた遺言内容を話すと作成ができないことがありますので注意してください。
③ 遺言者が口述した内容を、公証人が筆記して遺言者及び証人に読み聞かせます。
本人確認や③の確認が終わったら、公証人は遺言の内容を読み始めます。本人と証人の手元に同じ内容の遺言書を渡してくれますから、本人は手元の遺言書を見ながら公証人の読み上げる内容を確認するだけです。
「第1条、第2条、・・・」と遺言書を公証人が全て読み上げますので、それに対して「はい、大丈夫です。」と遺言者は回答すればよいのです。
④ 本人及び証人は、筆記の正確なことを確認し、署名押印
読み聞かせが終わると、公証人から「署名捺印してください。」と言われますので、公正証書遺言の最終ページに、遺言者及び証人2名が署名押印をします。
なお、本人が不自由でサインできない場合でも、公証人がその旨を遺言書に書いてくれますので、遺言書の作成に問題はありません。
⑤ 最後に公証人が署名押印して終了です。
最後に公正証書遺言の作成費用を精算したら完了です。
①公正証書遺言(原本)
②公正証書遺言(正本)
③公正証書遺言(謄本)
通常は、合計3通が作成されます。
原本はその公証役場に保管され、正本と謄本を受け取ることができます。
なお、遺言執行者が正本を、本人が謄本を保管することが多いです。
遺言書に「正本」「謄本」と書かれていますので、ご確認いただくことができます。
*公証人によって質問や方法が異なる
一般的な流れを説明してきましたが、実は公証人によって質問内容・流れ・やり方などが異なることが多いのです。
なにも質問することなく、いきなり遺言書を読み上げて署名押印してあっという間に終了する公証人もいれば、遺言者に対して面接官のようにいろいろな質問をする公証人もいます。
これは、公証人次第ですから、当日になってみなければわかりません。厳格に本人確認や意思確認をするという意味ではいいのかもしれませんが、男性の公証人で本人が緊張してうまく回答ができなくなることもあります。
緊張する本人の方へ
当センターでは、数百件も遺言書作成をしていますから緊張はありませんが、やはり本人や同行した親族の方々はとても緊張されています。
公証人からの質問に緊張されて、質問に答えられるか、不安が一杯で緊張した様子で公証役場に入られます。
しかし、当センターにご依頼いただいた場合は、親族の方は同席できませんが、当センターの行政書士等がご本人の隣に証人として座りますので、良いフォローができますので安心です。不安な気持ちにならず、公証役場でお会いしましょう。

当日に作成できず作れないことはありますか?
残念ながら当日キャンセルになることはあります。
当センターの事例ですが、病院で本人と面談しての意思表示は確認できたのですが、作成日当日に公証人に出張してもらい病室で意思確認の場面になるとにまったく意思表示をすることができないことがありました。また、当日にいきなり本人は「俺は知らん、娘が勝手にやっていることだ!」と怒り作成が流れてしまったこともあります。
ところで流れてしまった場合は、原則として公証役場にキャンセル料を支払わなければいけません。
証人2名はどこで探すのですか?
公正証書遺言を作成する時には作成時に立ち会う証人2名を用意する必要があります。本人の関係者や、親族だと証人欠格に該当する場合がありますので、通常は相続とは関係のない第三者の証人を探す必要があります。
なお、当センターに証人のご依頼をいただいた場合には、当センターの有資格者と事務員が証人として遺言書作成に立合います。
証人及び立会人の欠格事由
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公正証書遺言の作成と当センターの関係
公正証書遺言の原案作成は、原則として行政書士と弁護士が国家資格者としてお受けできます。(司法書士は、登記に関する遺言書の作成に限定されています)
費用面や専門性から依頼先を探されると思いますが、一般的には、相続が発生した場合に確実に争うことがわかっているのであれば弁護士に依頼することになるでしょう。それ以外は、遺言作成業務に経験のある行政書士に依頼をすることが一番だと思います。
なお、当センターの公正証書遺言の作成方針はこちらです。料金等も含めて書いておりますのでご依頼の参考にしてください。
➡公正証書遺言の作成業務はこちらから
遺言作成の専門家は調整役
実務では代理人として行政書士等が事前に遺言作成者のお話を聞いて、ご意思に沿った遺言書の原案を作成します。そして事前に公証人と打ち合わせをしてまいりますので遺言作成者の手間と負担は少なくなります。
公証人と事前に打ち合わせをすることができますので、当センターの行政書士がご意思を伺い入る方が原案の手直しもスムーズにできますので不備もほとんどなく公正証書遺言ができあがります。公証人からは当センターのように専門家が間に入ったほうがいいというのが本音かもしれません。
専門家が証人になるメリット
当センターが遺言作成をお受けした場合、通常は当センターの有資格者が証人となります。
証人欄には行政書士名が入ることで信頼感がありますから、第三者でしかも相続の専門家に依頼をして作成した内容であることで相続人同士の紛争の防止にも役立ちます。
公正証書遺言の公証人手数料
公正証書遺言は自筆証書遺言と違って公証役場の手数料や証人の報酬が発生します(*遺言作成者が自分で証人を探せば報酬はありません)。公証役場に支払う手数料は次の通りです。
遺言に記載する財産の価額
手数料
100万円まで5000円
200万円まで7000円
500万円まで11000円
1000万円まで17000円
3000万円まで23000円
5000万円まで29000円
1億円まで43000円
1億円を超え3億円まで5000万円ごとに1万3000円、
3億円を超え10億円まで5000万円ごとに1万1000円、
10億円を超える部分は5000万円ごとに8000円がそれぞれプラスされます。
なお、1億円以下の時は、更に手数料額に11000円がプラスされます。
例:
遺言で3人に遺贈する旨書いた場合、甲1000万円、乙2000万円、
丙500万円の内容の場合
17000円+23000円+11000円+11000(1億円以下加算)=62000円となります。
※公証人が出張の場合は手数料が1.5倍。
また、公証人の日当2万円(4時間まで1万円)別途交通費。
公証人手数料は3~8万円程度が目安。
公証人手数料は作成時点の価格で算定
公証人手数料は、遺言作成時点の価格で算定します。正確にいえば、公証役場へ提出した財産資料によって手数料が決まります。
公正証書遺言作成の必要書類
原則的な必要書類は以下の通りです。
(※事案により追加の書類が必要になる場合があります。)
・作成者本人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・作成者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
・財産資料一式
※預貯金の通帳など。
※株式は、取引残高報告書など。
※不動産は登記事項証明書と固定資産税の課税明細書など。
*公証役場により必要書類が異なる場合もあります。事前の確認が必要。
遺言書作成時に遺留分を考慮すべきか?
遺言書の作成では、遺留分のことを考慮しておかなければいけません。
たとえ、一部の相続人に財産を渡さない内容で遺言書を作成したとしても、遺留分を有する相続人は、相続時に当該遺留分の侵害額を請求することができるからです。
なお、自筆証書ではなく公正証書で遺言書を作っても、遺留分を打ち消すことはできません。
遺留分については、専門家によって考え方が異なるようです。次のように2つの選択肢が考えられます。
1.遺留分を考慮した内容で遺言書を作成
遺言書を作成する時点で遺留分を考慮して相続分を決める方法です。例えば、8分の1の遺留分を有することが想定される相続人がいるなら、当該相続人には8分の1の割合を指定して相続させる内容の遺言を作ります。
2.遺留分を無視して遺言書を作成
遺留分の内容を無視して遺言書を作成する方法です。つまり「相続開始時に遺留分の請求をされたら、その時に考えよう。」ということです。実際に遺留分を請求されるかわからないケースなど、こちらを選択される方がいます。
*重要です
当センターのご依頼者様は2を選択される方もいます。対応する事務所や信託会社によっては、遺留分を侵害する内容での作成依頼を受けない場合があるようです。当センターでは、きちんと遺言作成者にご説明して原案作成に着手いたします。
特別な公正証書遺言作成のケース
日本語は話せないが公正証書遺言は作れるか?
遺言者本人が日本語を話すことができなくても、通訳を介して公正証書遺言を作成することができます。なお、通訳者も、公正証書遺言に署名捺印が必要となります。ご注意ください。
言葉を発することができなくても公正証書遺言を作れる?
病状などによっては、言葉を発することができない場合があります。その場合も、公証人に対して身振り等で答えることができれば作成ができます。実際の現場で、「はいならば頷いて、いいえなら首を振ってください」という公証人からのメッセージで遺言作成ができた例が当センターは立ち会い作成ができました。
シールド越しの面会で公正証書遺言を作成した
原則として公証人と対面の面談が必要となっています。しかし、病気などで、施設の内部に入れずシールド越しで口述する場面に当センターでは立ち会いました。このケースではインターフォンで口述を行うことで作成できました。
公正証書遺言のまとめ
最も安全で確実な遺言作成が公正証書遺言です。
しかし、作成するために証人2人を用意しなければなりません。
また、公証人が作るためほぼ無効にはなりませんが、打合せの手間と公証人費用が必要です。
ところが、家庭裁判所の検認手続きは不要なので相続発生後すぐに遺言執行ができます。
原本は公証役場に保管されるため紛失や書き換えられる恐れもありません。
公正証書遺言の作成したいとお考えの方
公正証書遺言の作成を任せる事務所をお探しの方
相続相談福岡センターへご相談ください!
確実に安全、安心の遺言を作るには公正証書遺言が一番です。しかしながら、費用が発生しますし、遺言の作成をするための公証人との打ち合わせや、必要書類の収集に大きな手間と時間がかかります。気持ちよく公正証書遺言を作成するためには、遺言作成の経験豊かな専門家に依頼するのがよいでしょう。
当センターは、公正証書の遺言作成のご依頼を積極的にお受けしております。お客様のご意思を確実に相続で実現できるよう、どういった文案にすべきか、二次相続まで見通して、最初の指定した人が遺言者が先に死亡した場合などのリスクを予想したアドバイスもさせていただいております。
ご相談お申込みフォーム
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com



