相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
相続が確実にできる遺言作成の
ポイント知っていますか?
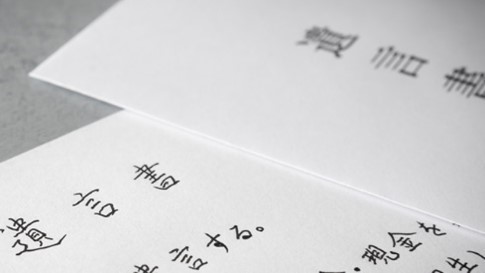
相続が確実にできる遺言作成のポイント知っていますか?
遺言書のポイントとは、確実に相続手続きができる遺言書かどうかが問題です。ご存じでしょうか?
遺言書の目的は「作成すること」ではなく、「相続手続ができること」なのです。そもそも遺言書の作成の目的は「人生の最後の手続き」がキチンとできるかという相続のキモともいえる部分です。
だから遺言書の必要性は多くの人が感じているのですが、その理由を把握している遺言者は少ないのではないでしょうか。
遺言書には作成方法で大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言になります。
また、R2年7月から始まった法務局による自筆証書遺言の保管制度は、遺言書を自分で作成したいと考えている方にとっては追い風になり急速に増えています。
その理由は、遺言書を自分で書くことが、内容にもよりますがそんなに難しくないと思っている方が多いからです。
そもそも、自筆証書遺言とは「すべて自筆」、要するに手書きの遺言書のことです(財産目録はPCで作成し預金通帳などはコピー添付も可となりました)。ただ、私たちは相続の専門家が、なぜ公正証書遺言を勧めるのか考えて頂きたいのです。
では、その理由をお話ししましょう。
例えば「自宅を妻に相続させる」場合でお話をします。
まず、「自宅」と遺言に書いても、自宅がどこの不動産か、土地だけなのか建物も含むのかなどは、わかりません。
最低でも「自宅」の土地や建物が特定できるための情報を書く必要があります。
その理由は、不動産の特定ができないと、自宅を妻に名義変更することができない可能性がでてくるからです。
遺言を書く際にも、相続人には「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」という書き方は基本中の基本ですが、相続人に「遺贈させる」と遺言に書くと、登記手続では遺贈扱いになり、不動産の場合には登録免許税が5倍も高くなる可能性があります。
また、登記修正の方法にもルールがあり、間違えるとその部分だけ無効扱いになってしまいその部分だけのために遺産分割協議をする必要になったり、遺言執行者が指定されていないと、遺言者が亡くなったあとに、家庭裁判所に申立をして遺言執行者を選んでもらう必要が出てきます。
いずれにしても、夫婦はどちらが先に亡くなるかわかりません。
夫が全財産を妻へという遺言を書いていても、夫より先に妻が亡くなった場合には、妻に渡そうとした財産は宙に浮いてしまいます。
さらに、妻が先に亡くなった場合に「長男に相続させる」と書けば(これを予備的遺言といいます)、長男に相続させられますが、この予備的遺言がなければ、財産は宙に浮いた状態となり遺産分割協議を行うことになります。
残念ながら遺言書に書いてないと、遺言で相続できる財産と、遺言書で執行できずに遺産分割協議の話し合いになる財産に分かれることになるのです。
つまり中途半端に遺言を書いたことが相続においてはもめる原因になりかねないのです。
だから遺言を書く際には、最後まで遺言に書いたとおりに相続手続ができるようにするために、遺言書は考えられるすべてのケースを考え、予備的遺言も含め作成することが重要になります。
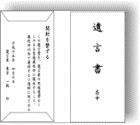
自筆証書遺言作成上の注意点
2020年7月から自筆証書遺言を法務局で預かる保管制度が始まりました。
法務局が自筆証書遺言の原本と画像データを保管するため遺言の紛失や改ざんが防げるほか、遺言者が亡くなった場合は、指定された人に遺言書が保管されている旨の通知も送られます。
申請手数料は3,900円なので作成希望者は多いようです。また、法務局に保管すれば家庭裁判所の検認が不要になることもメリットです。
しかし、ここで注意しなければならないことがあります。必ず遺言者本人が法務局に出頭して、顔写真付きの本人確認書類を提示しなければならないのです。
また、遺言書の用紙のサイズや余白などの規則が細かく決められているため、注意が必要ですし、サイズ等を守っていないために受け付けてもらえないということも起こります。
なかでも、問題は相続発生後に、遺言書を「法務局から取り出せない場合がある」という点には注意が必要です。
まず、相続が発生すると、法務局から遺言者が指定した人に「指定者通知」が送られます。通知された人は「遺言書情報証明書」(=遺言書の画像データ)を請求したり、遺言書の原本の閲覧ができます。
ここで、手続きには「法定相続情報一覧図」または遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本と住民票(写し)が必要になります。
ここで問題になるのは、親子の戸籍謄本は「上下」は簡単に取れますが、兄弟の戸籍謄本「横」は簡単には取得できないのです。
例で申し上げると、父が亡くなり相続人は母と3人の子どもというケースでは、相続人は被相続人(亡くなった父)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を、広域交付制度を利用してどの自治体からでも入手できます。
しかし、相続人が妻と夫の兄と姉の場合は、相続人を確定するためには、夫と、夫の父と母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等が必要になります。
妻は夫の出生時からの戸籍謄本等は広域交付制度を利用して取得できますが、夫の父母の戸籍謄本等の取得は広域交付制度の対象外になるため取得できません。
夫の本籍地が生まれてから死亡するまで、A市、B市、C市と転籍をしていたら、死亡時の本籍地C市から出生時の本籍地A市まで遡って入手する必要があります。
これは、母の場合も同様です。
つまり異父・異母兄弟姉妹等がいるかどうか調査しなければならないからです。
ここで、ケースによりますが、戸籍謄本等の取得に行き詰り、専門家に依頼することもあり得るのです。
また、相続人の兄弟姉妹が確定しても再婚相手の子どもの場合などで、交流がなく住所も不明、という場合も起こりえます。
だったら大変な法務局に預ける保管制度は使わずに遺言書を自宅に保管しておけばいいのではないかと考えるかもしれません。
ところが、この場合は遺言者が亡くなったときに家庭裁判所の検認が必要になります。
しかし、この検認の申立て時にはこの戸籍謄本等が必要になります。
ではどうすればいいのか。
しれは、元気な今専門家に依頼してすべての書類を整えてもらい、予備的遺言なども含めた内容で公正証書遺言を作成したほうが相続人は困らないということではないかと思いますがいかがでしょうか。
なお、ちょっと頭を冷やして聞いてほしいのですが、「法定相続情報一覧図」は、法務局で交付してもらうのです。
この一覧図は、預貯金の解約や相続登記、相続税の申告など、相続手続きで戸籍謄本等の代わりに利用できる公的証明書です。
しかし、この一覧図を交付してもらうにはやはり相続人を確定させる戸籍謄本等が必要になるのです。

こんなケースはいますぐ作成を
必ず遺言書を作成しておきたいケースがあります。
まず、誰も相続人がいない人、次にて子どもも両親も祖父母もおらず、兄弟姉妹が相続人となる人です。
なかでも配偶者と兄弟姉妹間が相続人の場合、遺産分割協議は必ず配偶者が大変になります。
しかし、兄弟姉妹は遺留分(相続できる最低限の割合)がないため、遺言書を作成して配偶者に相続させたい財産を決めておくと夫の全財産を配偶者に相続させることができ、配偶者の相続における心配事は大幅に減少します。
また、前婚の配偶者との子どもが相続人の場合や、住所も知らないし交流がないし、行方さえわからない相続人がいるケースも同様です。
なかでも相続人が行方不明の場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人をつけてもらい、遺産分割を行う必要があります。
さらに、判断能力のない相続人がいる場合は、後見人等を選んだもらい遺産分割を行う必要が出てきます。
そもそも後見人がいない場合は家庭裁判所に選んでもらい、その後見人に遺産分割とその後の財産管理を行ってもらうことになります。
このような特別なケースには、遺言書の作成を強くお勧めしています。
ご相談でよくある例ですが、「遺産分割協議では法定相続分で分けないといけない」と誤解している相続人は多くいらっしゃいます。
だから、「法定相続分で分けたくないから、遺言書を作る」と考えている方がいます。
「遺産分割協議では自由な割合で決められます」とアドバイスさせていただくと驚かれますが、家族の仲が良くて、相続の話し合いでまとまるなら、遺産分割協議で自由に遺産を分けていいのです。
ところが専門家の視点はそこではないのです。
今は家族仲が良くても、遺産分割がスムーズに進まない場合や相続手続きが大変になる場合は、遺言書はあると問題も起きませんし、遺言書を書くなら早く作ったほうがいい、という結論になるのです。
残る家族のことを思って判断しましょう
公正証書遺言の作成はどれくらいの費用がかかるのか、だれしも気になるところでしょう。
簡単な内容の遺言の場合には、ご本人が直接公証役場へ行き、作成してもいいと思います。
なお、公証役場の手数料は全国一律ですが、どの相続人がどのくらいの額の遺産を相続等するかで、受け取る遺産の額に応じた手数料が1人分ずつ加算されていきますので、遺言書に登場する相続人等の人数と遺産の額が多くなれば高くなっていきます。
それでも、一般的には、4万円台から10万円位を目安にするとよいでしょう。
なお、公証人は「相続対策」までは相談を行わないため、込み入ったご家庭のケースは、やはり作成サポートを相続専門の行政書士や弁護士に依頼するほうが無難です。
ただし、その費用は専門家によって様々ですが、「あなたが生きているうちにお金を使い家族が困らないようにしておくか、亡くなった後に相続人が争いになりお金や時間の負担をしてもらうか」の違いだと考えてみては如何でしょうか。
あなたには遺言書が必要か、作成は自筆証書遺言、公正証書遺言どちらがいいか。遺産の額ではなく、あとに残された家族の状況をもう一度想像してみて、検討されてはいかがでしょうか。
ご相談お申込みフォーム
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com



